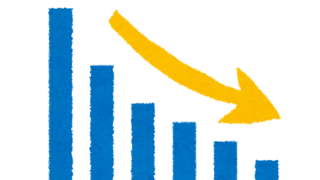 教師不足
教師不足 少子化なのに教員が足りない理由
昨今、教員不足が言われていますが、少子化も進んでいます。「なぜ、子どもの数が減っているのに、教員が足りないのか?」と思っている人のためにその理由を解説します。
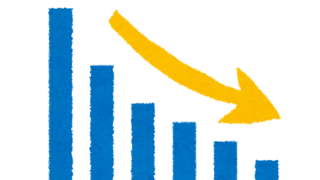 教師不足
教師不足  教育政策
教育政策  教育政策
教育政策  教育政策
教育政策  教育政策
教育政策 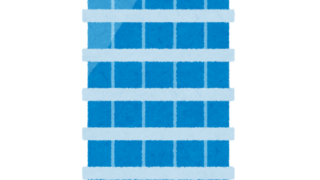 業務効率
業務効率  業務効率
業務効率  業務効率
業務効率 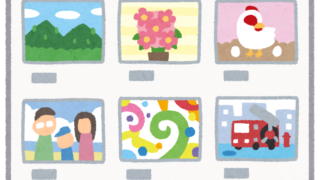 業務効率
業務効率  教育政策
教育政策