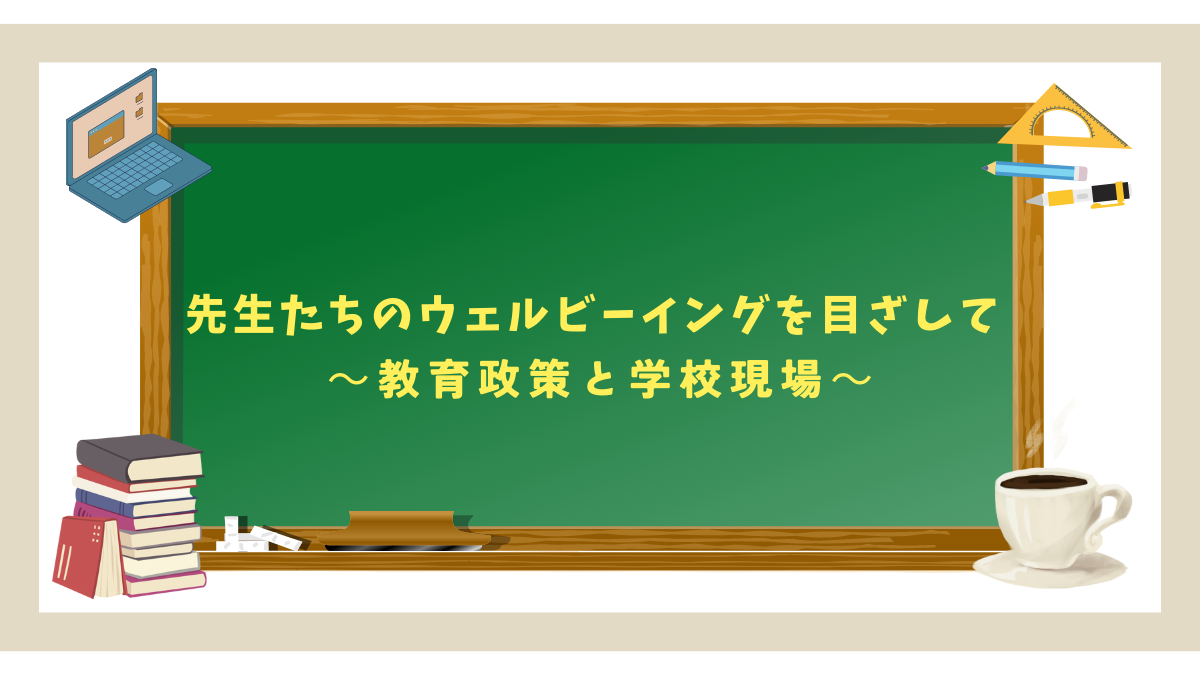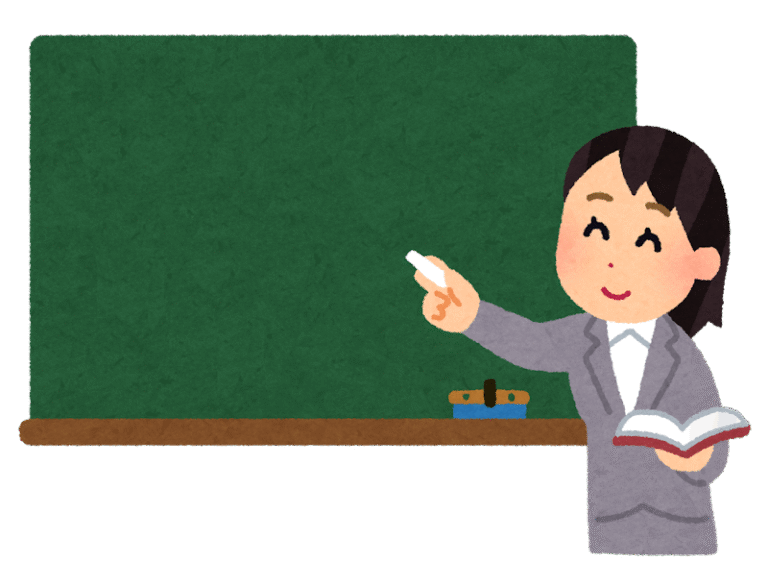今年(令和7年)6月、国会で成立した改正給特法等は、教職調整額が段階的に10%に引き上げられることが大きな注目を浴びましたが、実は同法の「附則」第3条の中に今後の学校の働き方改革の方向性に関することが明記されています。
この「附則」第3条を受け、中教審にも新たな部会(「教師を取り巻く環境整備特別部会」)が設置され、7月から議論が始まっています。
そこで今回は、「附則」第3条をもとに今後の学校の働き方改革に関することを書きたいと思います。
本記事を読めば、学校の働き方改革が今後どのように進められていくのかわかると思います。
結論を先に言えば、時間外勤務の平均を月30時間にすることを目指し、教員1人あたりの授業時数を削減するなどとしています。
以下、詳しく見ていきます。
時間外勤務の目標値と学校の現状
まず、「附則」第3条の冒頭の部分を紹介します。以下のようになっています。
政府は、令和11年度までに、公立の義務教育諸学校等の教育職員について、1箇月時間外在校等時間を平均30時間程度に削減することを目標とし、次の措置を講ずるものとする。
期限と目標が具体的に示されているのが特徴です。1ヶ月あたりの時間外勤務は、令和2年(2020年)に策定された指針により、現在月45時間を上限としているのは全国の先生方も知るところと思いますが、これを15時間も減らして30時間を目標とするというのです(あくまで「平均」ですが)。
現場の人間から言わせてもらえれば、現状では月45時間すらかなり難しいと思っています。ちなみに、僕自身はおおよそ勤務開始時間の30分前には学校に行き、授業の後、部活動指導に行けば勤務終了時間から2時間〜2時間半は経過しています。その時点で退勤したとしても、1日あたりの時間外勤務は平均3時間程度であり(実際は部活動終了後も業務をすることがあります)、1ヶ月に約20日働くとしたら、単純計算で約60時間になります。
これを30時間とするなら、1日あたりの時間外勤務の平均は1時間30分となります。つまり、仮に8時15分勤務開始、16時45分勤務終了であり、7時45分から勤務を開始するとしたら、17時45分には退勤しなければなりません。
これを実現するためには、中学校の場合、少なくとも①授業の空きコマを増やす(=教員を増やす)、②学校部活動の廃止をしなければなりません。
具体的な方策
そこで、「附則」第3条には以下の7点が示してあります。まず、3つです。
①教育職員1人当たりの担当する授業時数を削減すること
②教育課程の編成の在り方について検討を行うこと
③公立の義務教育諸学校等の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(義務標準法)に規定する教職員定数の標準を改定すること
①にはやはり、授業時数を削減することが書かれています。ただ、これは中学校と高校は可能と思いますが、小学校では難しいのではと思ってしまいます。小学校も教科担任制が増えつつあるとは聞きますが、全ての学校で導入するのは難しいのではないかと思います。
②については、授業時数をどう考えるかという話になります。今回の会議資料に「現行の教育課程の下で具体的に週当たり時数を減らす工夫」(資料04-02)という資料が掲載されており、全国の学校の好事例が紹介されています。興味のある方は本記事末尾のリンク先から資料をご覧ください。
また、教育課程の工夫については以下の記事をご覧ください。
③については、学校の働き方改革の最も大事な部分になります。ただ、昨今のなり手不足の現状から、教員の定数を改善したところで、その枠を埋めることができないのではないかと思います。
残り4つは以下のとおりです。
④教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること
⑤不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと
⑥部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと
⑦①~⑥のほか、教育職員の業務の量の削減のために必要な措置
④は近年増えつつある教員業務支援員等を想定していると思います。
⑤は僕自身はそこまで経験はないですが、保護者が「お客様化」してしまっている現状の中、難しい部分がありますが、支援の仕方次第ではありがたいものになると思います。
⑥が時間外勤務及び土日等の業務を劇的に減らすためのカギであるのは言うまでもありません。部活動の地域展開については以下の記事をご覧ください。
最も必要な施策は?
さて、最後に①〜⑥の中で学校現場で最も必要な施策について、僕の個人的な意見を書きます。
それは④の「教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材の増員」です。他のももちろん必要なのですが、正直なところ、実現の可能性は低いと思います。
学校現場の業務というのは実は、教員でなくても、つまり教員免許を所有していなくてもできることがたくさんあります。教員免許が必要なのは授業くらいです。それ以外の業務を教員業務支援員等にしてもらうと、教員は本務である教材研究にかなりの時間を割くことができ、授業の質が向上します。
実際、今年度、僕が勤務する学校に教員業務支援員が配置されましたが、大変助かっています。今のところ、1名しか配置されていませんが、学年に1名配置していただくともっとありがたいと思っているところです。
教員業務支援員等のなりては地域にたくさんいると思います。それは、教員を退職した方々です。その方々が謙虚な姿勢で学校に力を貸してくれると学校は助かると思います。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今後、文科省は教員の時間外勤務の平均を月30時間にすることを目指し、教員1人あたりの授業時数を削減するなどとしています。
正直、うまく進んでいくとは思えませんが、淡い期待を抱きながら、自分でも削減可能な業務はどんどん削減していこうと思います。
より詳しく見てみたい方は以下のページをご覧ください(資料03を参考にしています)。