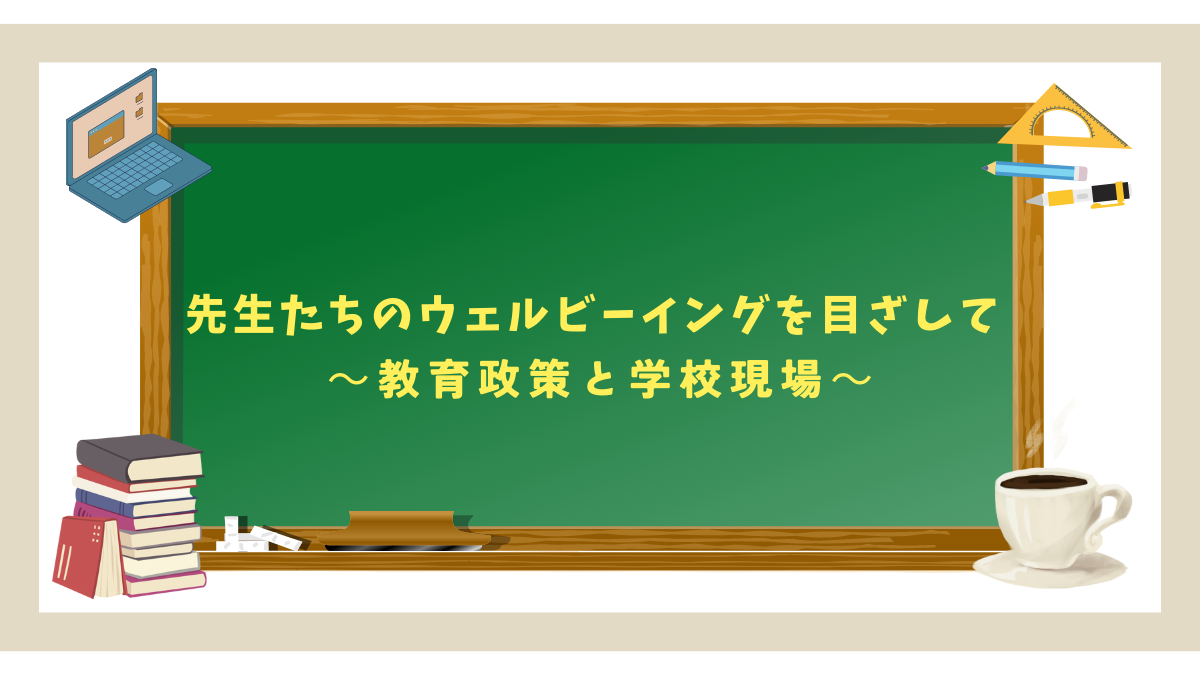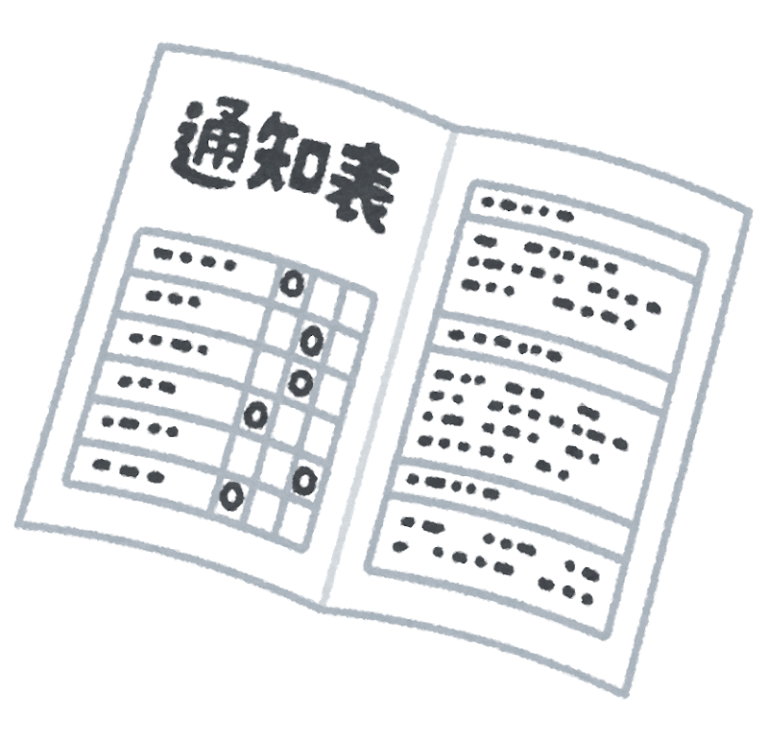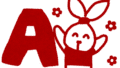全国の先生方、夏休みが近づいてきましたね。夏休みが近づくのは嬉しい反面、学期末には評価評定の算出や通知表の所見作成など、事務仕事も多くなります。
これらの事務仕事は重要なものですが、苦手意識をもっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、通知表の所見の書き方のポイントについて書きたいと思います。
本記事を読めば、通知表の所見に書くべきことやスムーズに書く方法がわかると思います。特に、若い先生方の力になれるのではないかと思います。
結論を先に言えば、①プロットを考えておく、②ネタを集めておく、③こまめに書くの3つです。
以下、詳しく見ていきます。
通知表の所見は縮小の傾向
冒頭に、「学期末」と書きましたが、夏休み前のこの時期に通知表を作成する学校は、地域にもよるでしょうが、今やずいぶんと減っているのではないかと思います。
従来の3学期制に代わり、2学期制の学校が随分と増えましたし、また、3学期制を維持しながら通知表の年2回としている自治体もあります。少なくとも僕の周りには、この時期に通知表を作成している学校はありません。
また、通知表の所見を廃止又は縮小する学校もあると聞きます。教員の負担軽減が主な目的だとは思うのですが、思い切ってゼロにする、又は年1回とする学校もあるようです。
ただ、個人的には所見を書くという仕事は、負担に感じる一方、教員としての大事な仕事だと思ってきました。そもそも僕はこのようなブログも書いていることからもわかるとおり、文章を書くのは好きですし、所見を書く作業というのは、学校生活の様子を家庭に伝える重要な手段だと思ってきました。ただ、多くの教員にとっては、重荷になっている現状があるようです。
校長や教育委員会の判断により、所見をなくした(又は縮小した)学校もある一方で、従来どおりの所見作成をしている方々に対して、あくまで僕個人の経験ですが、所見の書き方のポイントについて以下に書いていきます。
所見の書き方のポイント
それではここから、いくつかのポイントを書きます。
①プロットを考える
まずは、プロット(構成)を考えましょう。ちなみに、僕は1学期(前期)は、性格 → 委員会や係活動の様子 → 行事等での頑張り → 学習面の様子 → 次学期への期待という流れで書いていました。
このようにプロットを決めていると、次の文に何を書こうかと悩むことはないですし、全体の文量も同じくらいになってきます。
ちなみに僕は文量も概ね合わせていました。書くことが多い生徒、少ない生徒それぞれいますが、一律に250文字程度にしていました。そのようなルールを作っておく方が書きやすいと思います。
②ネタを集めておく
これが最も大事かと思います。上にも少し書きましたが、所見というのは書くことがありすぎるくらい、多くの活躍をしれくれる生徒もいますが、何を書けば良いのかというくらい、控えめな生徒もいます。
特に控えめな生徒は書くのに苦労しますので、日頃からネタを集めておくのが大事です。具体的には、給食や掃除のときの様子をつぶさに見ることや、何かを頼んだときの行動や態度を見ることです。例えば、「掃除の時間には、自分の担当場所を丁寧に雑巾で拭く姿が見られます」という感じです。
そして、このようなネタというのは必ず記録しておきましょう。学期末に生徒に学校生活の振り返り(キャリアパスポート)を書かせる学校も多いと思いますが、それとは別に教員から見た生徒の日々の記録をとっておくことが大事です。
③こまめに書く
これは先生方の性格にもよるでしょうが、所見に苦手意識をもっている先生ほど実践してほしいと思います。
一日に◯人書くというのを決めておきます。ちなみに僕は一日2人、そして一人あたりにかける時間は15分と決めていました。これなら、一日の作業時間は30分です。そこまで負担に感じることのない時間ですし、授業の空き時間にできると思います。締め切り日が出されたら、逆算していつから書く必要があるかを決めましょう。
さらに、書くときは規則的に書いた方が良いです。ネタがたくさんあり、書きやすい生徒から書くと、最初は順調に進みますが、後半に苦しくなり、書くのが辛くなっていきます。僕は名簿順の1番の生徒から順番に書いていました。
まとめ
いかがだったでしょうか。
通知表の所見の書き方のポイントは①プロットを考える、②ネタを集めておく、③こまめに書くでした。
とは言え、まだ所見を書いたことのない先生は実際に書いてみないと、うまくイメージがつかめないかもしれません。書いているうちにだんだんとコツをつかめてきます。所見作成に限った話でないですが、物事、実際に取り組んでみないと何も進歩しません。
所見の最大の最大の役割は、学校生活の子供の良い部分を家庭に伝えることです。それができると、保護者から「先生はこういうところを見てくれている」と思われるようになり、保護者からの信頼も増していきます。プロットは大事ですが、その生徒の頑張りが伝わるような表現が大切です。
表現力を高めるには、普段から読書することなども大事ですし、所見の例文はネット上は書籍に数多くあります。慣れないうちは参考にした方が良いと思います。
全国の先生方、大変な作業ですが、頑張りましょう!