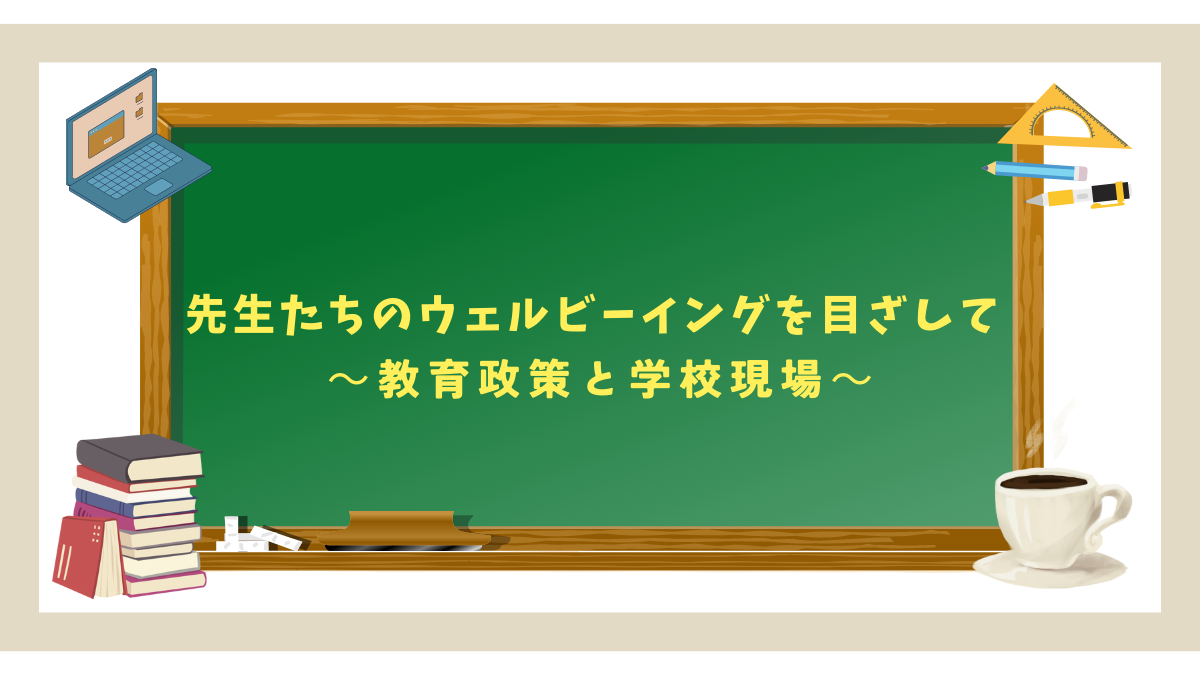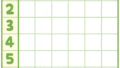皆さん、学力が高い国と言えばどこの国をイメージしますか?
かつてはフィンランドが有名でしたが、直近(2022年)に実施されたPISA(OECDが実施する学習到達度調査)では、シンガポールが全ての分野で1位を獲得しています。
そこで今回は、前回の記事で紹介した書籍の中から、シンガポールの学力が高い理由について書きたいと思います。
本記事を読めば、シンガポールの学力が高い理由がわかると思います。
結論を先に言えば、教師にゆとりの時間を確保していることです。
以下、詳しく見ていきます。
シンガポールってどんな国?
まず、シンガポールという国について一応説明します。
シンガポールと言えば、マーライオンが有名ですが、1965年にマレーシアから分離独立した都市国家型の国です。人口は約604万人(2024年のデータ。近年、外国人が増えているとのこと)、面積は約735k㎡で東京23区や琵琶湖とほぼ同じ大きさです。
日本はよく天然資源に乏しい国と言われますが、シンガポールは飲料水すら隣国マレーシアからの輸入に頼らざるを得ないほど天然資源に乏しい国らしく、そのため、人材を貴重な資源と捉え、教育に力を入れているとのことです。
シンガポールの基本的な教育制度
ではここから、シンガポールの教育制度について紹介します。
シンガポールは1965年の独立後、初代首相のリー・クアンユーが「シンガポールの唯一の資源である人材の育成」を掲げ、限られた資源の中での効率的な教育制度を築いたとのことです。
特徴的なのは、1980年に導入された小学校卒業試験(PSLE)で、この試験のスコアに基づき、中学校のコース分けをするようになったとのことです。
コースは、「エクスプレス」、「ノーマル(アカデミック)」、「ノーマル(テクニカル)」の3つからなり、最も高いスコアが要求される「エクスプレス」に進むために、子供も保護者も必死になったそうです。
しかし、想像できると思いますが、こうした受験戦争的な仕組みはしばしば子供や保護者に過度な負担を与え、「PSLEは重要だ」と感じる国民も多い一方、高ストレスになっているというアンケート結果もあるとのことです。
ただ、こうした取組の成果が近年のシンガポールの躍進につながっているそうです。
シンガポールの新しい取組
シンガポールは2000年、PSLEは続ける一方で、新しい教育プログロムを導入したとのことです。
それは、我が国が行っている「総合的な学習の時間」に近いもので、4〜5名のグループに分かれて、教科の枠組みにとらわれずテーマを決めて探究活動を行うそうです。
さらに2005年には、「TLLM(Teach Less,Learn More:より少なく教え、より多く学ぶ)イニシアチブ」というプログラムを始め、学習内容を削減し、学習の質の深さを目指すようになったとのことです。
こうしてシンガポールは、従来型の知識詰め込み型の教育もする一方で、アクティブ・ラーニング型の教育もしており、こうした取組を筆者は「巧みに緩急を使い分けている」と表現しています。
シンガポールの学力が高い理由
最後に、シンガポールの学力が近年伸びている理由を書きます。
もちろん、PSLEの成果もあるのですが、2005年に導入したTLLMにおいて、カリキュラムの削減を進める中で、教師に対してもゆとり(space)を作ることを徹底してきたとのことです。
具体的には、教師の数を増やすことはもちろん、スクール・カウンセラー、特別支援員、部活動支援員などのサポートスタッフを増やしたとのことです。こうすることで、教師が学習指導に専念する十分な時間を確保したとのことです。
ここに日本の教育との明らかな差が出ています。日本では「総合的な学習の時間」が導入されても、道徳が教科化されても、◯◯教育が増えても、教師数は増えていません(おそらく。増えたとしても微々たるものでしょう)。人は増えずに業務だけがどんどん増える「ビルド・アンド・ビルド」の状態になっています。
これは学校に限らず、どの仕事にも言えることと思いますが、本来なら、業務が増えればその分、人の配置をしなければいけないはずです。ところが、日本の教育はそれを怠ってきました。それが昨今の教師不足にもつながっている部分があります。
シンガポールのこうした取組は、日本も見習うべきところが多いですが、残念ながら現状では難しいいところでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
シンガポールの学力が高い理由は、教師に対してゆとり(space)を作ることを徹底してきたためです。教師以外の人材を学校に配置し、教師の業務を絞ったことで、教師の働きやすい環境を作ることに成功し、それが子供に還元されています。
なお、シンガポールの教育政策について、より詳しく知りたい方は、前回の記事で紹介した白井俊著『世界の教育はどこへ向かうか』(中公新書、2025年)をお読みください。