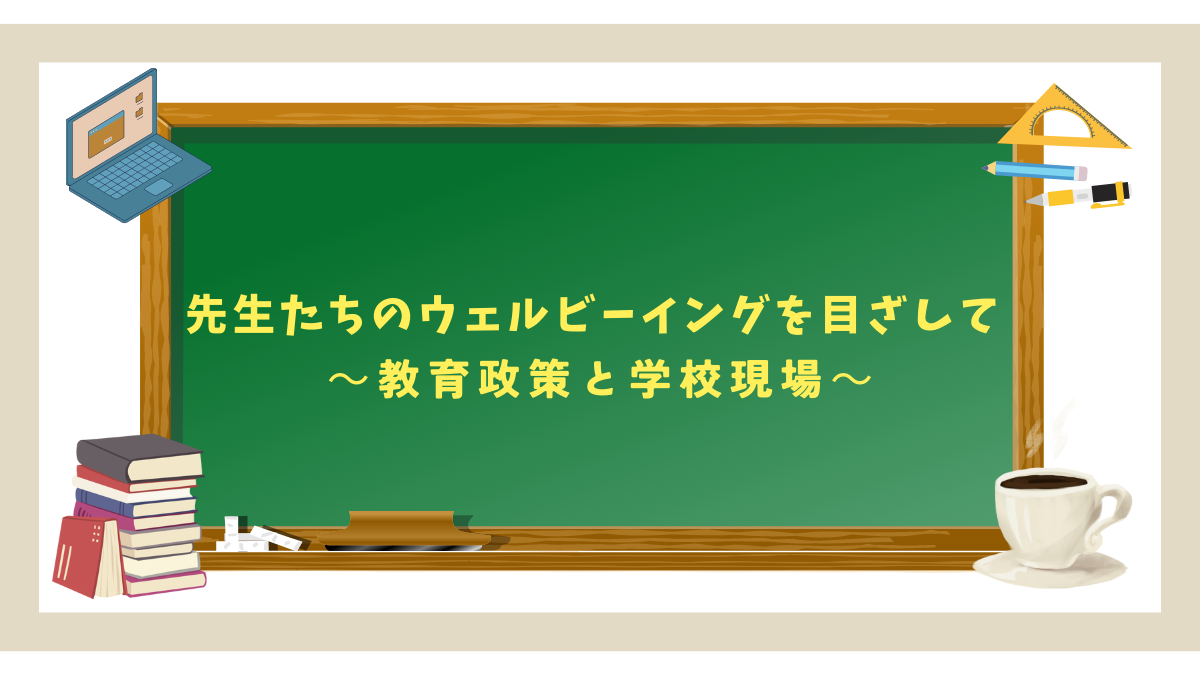先日(令和7年5月16日)、中学校の部活動改革について議論を進めてきた国の有識者会議が今後の改革の方向性について最終とりまとめを行いました。
そこで今回は、中学校の部活動が今後どのような方向性で改革が進められていくのかということについて書きたいと思います。
本記事を読めば、中学校の部活動の在り方の今後の方向性がわかると思います。
結論を先に言えば、中学校の部活動は今後、「地域展開」へと名称を変えること、そして、令和8年度からの6年間を「改革実行期間」とし、「休日については次期改革期間内に原則、全ての部活動において地域展開の実現を目指す」こととしています。
以下、詳しく見ていきます。
これまでの経緯
中学校の部活動については、少子化により学校単位での活動が難しくなっていることや、教員の時間外勤務の増加につながっていることから、数年前から学校から地域に活動の主体を移そうとする改革が進められてきました。
具体的には、令和5年度(2023年度)から令和7年度(2025年度)までの3年間を「改革推進期間」とし、主に休日の部活動を地域のスポーツクラブや文化芸術団体などが担うことを目指してきました。
今年度が「改革推進期間」の最終年度にあたるわけですが、皆さんの自治体では地域移行は順調に進んでいるでしょうか。僕の周りでは、あまり多くの事例は聞きません。クラブチームは増えてきたなという印象は受けますが、「移行」しているという印象はあまり受けません。あくまで、別の団体として活動しています。
ところで、部活動の地域移行が進まない理由については以下の記事を参考にしてください。僕なりの分析ですが、おそらく的を射ているのではないかと思います。
また、部活動の地域移行をせず、学校主体の部活動を継続しようとしている熊本市の部活動改革についは、以下の記事をご覧ください。
今後の改革の大きな柱
では、これまでの経緯をふまえ、今後の方向性はどうなるのでしょうか。
まず、改革を進めていくうえで、国は2つの大きな柱を設定しています。
①「地域移行」という名称を「地域展開」へ変更
②令和8年度(2026年度)からの6年間を「改革実行期間」とする
①については、「学校内で運営されてきた活動を広く地域に開き、地域全体で支えていく」ということをコンセプトとしたうえで、「学校部活動から地域クラブ活動に転換した場合であっても、地域クラブ活動の実施に当たって、学校施設の活用等、学校との連携は図る必要」としていますが、「移行」という言葉を使うと、部活動が学校主体から地域主体になり、学校から部活動がなくなるという印象を持たれますし、完全に「移行」するのは難しいという判断でしょう。
②については、令和8年度(2026年度)から令和10年度(2028年度)までを前期、そして「中間評価」を経て、令和11年度(2029年度)から令和13年度(2031年度)までを後期としています。今回の3年間ではあまりうまく進まなかったので、倍の6年間にしたような印象を受けます。
今後の具体的な方向性
では、ここから具体的な方向性について見ていきます。
まず、前提として以下のような文言があります。
地方公共団体が幅広い関係者の理解と協力の下、平日・休日を通した活動を包括的に企画・調整し、多様な選択肢の中から地域の実情等にあった望ましい在り方を見出し、改革の方針を決定することが重要(生徒・保護者等への丁寧な説明も必要)。
上にリンクを貼った記事でも書いていますが、これが非常に難しいのです。「地域の実情」は地域により全く異なりますので、それに応じた制度を構築するというのはかなりの労力なのです。とは言え、国が一律に決められることでもありませんので、部活動改革は難航しているのです。
そして、以下の3つの方向性を示しています。
①休日については、次期改革期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す
②前期の間に確実に休日の地域展開等に着手
③受益者負担と公的負担とのバランス等の費用負担の在り方等を検討する必要
①については、「できる限り、前倒しでの実現を目指すことが望ましい」としていますので、急かしている感じがあります。
しかしながら、「実現することが望ましい」ではなく、「実現を目指すことが望ましい」という表現が気になります。地域展開を実現しなくても、実現しようと動いていれば「目指している」ことになります。このへんの言葉の使い方はさすがだなと思います。
②については、やはり言葉の使い方が気になります。「着手」なのです。つまり、実現しなくとも、実現に向けて動いていれば「着手」していることになります。
ところで、我々現場の教員が感じていることは、結局、休日のみ部活動が地域に移行しても、平日がなくならないなら、あまり変わらないということです。
つまり、休日は平日の練習の成果の確認をする場や集大成の場である、練習試合や大会があることが多く、平日の練習を指導するなら、練習試合や大会等も見たい、見なきゃならないと思うのが教員の性です。それを割り切れる教員はあまりいないのではないかと思います。
平日の地域展開については、「できるところから取り組む」、「前期において活動の在り方や課題への対応策等の検証を行った上で、中間評価の段階で改めて取組方針を定め、更なる改革を推進」としており、更に弱い表現となっています。指導者の確保等の観点から休日以上に難しいというのが実情でしょう。
③については、家庭の経済格差により、子供がスポーツ等に親しむ機会が失われることが懸念されていますので、今後、慎重な議論が必要でしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
中学校の部活動は今後、「地域展開」へと名称を変えること、そして、令和8年度からの6年間を「改革実行期間」とし、「休日については次期改革期間内に原則、全ての部活動において地域展開の実現を目指す」こととしています。
より詳しい内容をご覧になりたい方は以下のリンク先をご覧ください。
また、このページには全国の自治体の取組事例集も掲載されていますので、担当の方は参考になるかと思います。