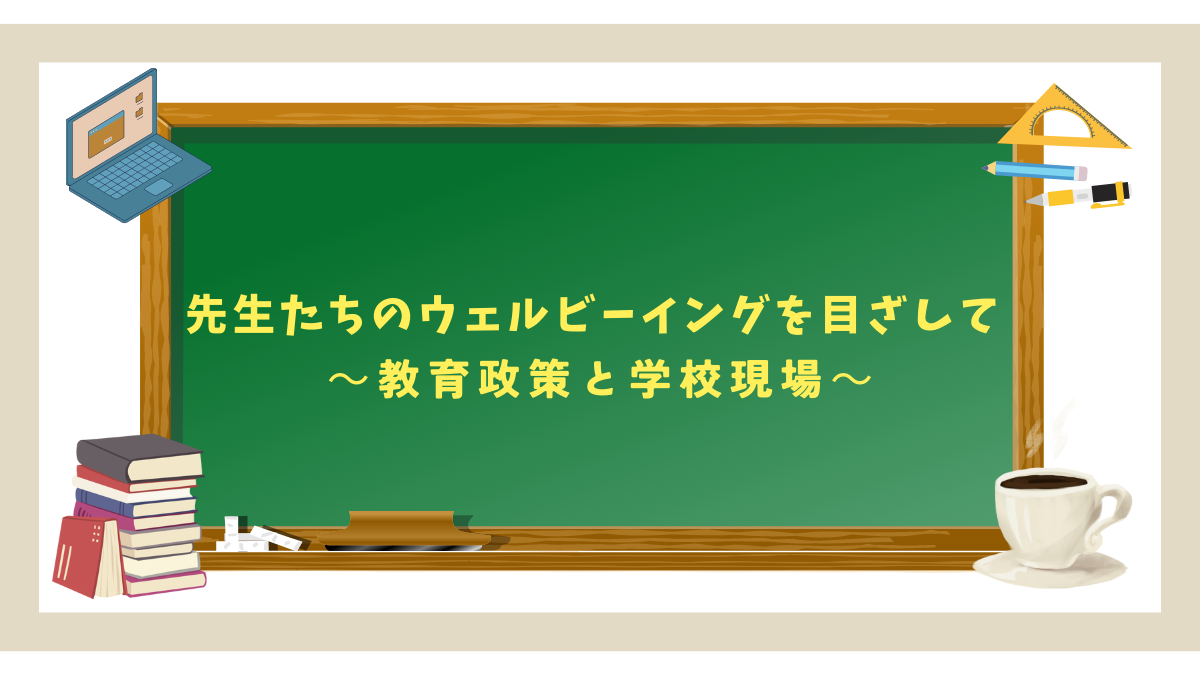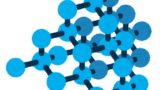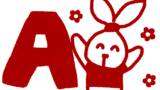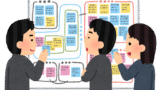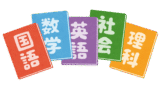前回の記事でも書きましたが、今月初め(令和7年9月5日)に次期学習指導要領策定に向けた論点整理(素案)が中教審の特別部会で示されました(後日、「案」を経て確定されました)。
前回の記事では、次期学習指導要領の基本的な考え方について書きましたが、今回は、本ブログの過去の記事を引用しながら論点整理のポイントを書きたいと思います。
本記事を読めば、令和12年度(2030年度)から小学校で全面実施される予定の次期学習指導要領のポイントについてわかると思います。
以下、詳しく見ていきます。
論点整理とは?
まず、論点整理の位置づけについて書きます。
中教審は、文科省から教育課題や教育政策について諮問を受け、議論を始めますが、一定の議論を経た後、今後さらに議論すべき論点をまとめます。これが「論点整理」です。
その後、さらに細かい議論を進め、「審議まとめ」そして「答申」へと至ります。「諮問」や「答申」はニュースになりやすいため、聞いたことがある方も多いと思います。特に「答申」は最終結論ですので有名ですよね。
今回は、議論の途中段階である「論点整理」ですが、おそらく大きな方向性は今後変わることはないと思いますので、「論点整理」を見ておくと、次期学習指導要領の方向性が掴めると思います。
なお、今回公表された「論点整理」(素案)は、第1章から第8章まであり、スライドが113枚もあるかなりボリュームのあるものですので、ポイントを絞って書いていきたいと思います。
分かりやすく、使いやすい学習指導要領へ
では、ここから次期学習指導要領のポイントです。
学習指導要領は、授業構想にあたって重要なものであることは言うまでもないですが、いかんせん活字ばかりで大変難解に感じますよね。本来なら、毎回の授業の度に目を通さなければならないものですが、現場の人間にそんな余裕はないため、研究授業の際にしか見ていない教員がほとんどではないかと思います。
そのような実態を踏まえ、次期学習指導要領は、諸外国の例を参考に「中核的な概念」等を中心に目標や内容等を構造化し、さらに、見やすく・使いやすくするために表形式化・デジタル化することを検討しています。
「中核的な概念」は次期学習指導要領のキーワードになりそうな気がします。詳しくは以下の記事をご覧ください。
構造化については以下の記事をご覧ください。
デジタル化については、以下の記事をご覧ください。
「中核的な概念」等を中心に構造化したもののイメージが以下のものです(中学校数学「数と式」)。

(出典:文部科学省HP)
現在の活字だけのものより、はるかに見やすく、わかりやすいですね。単元ごとの「中核的な概念」等を獲得するために学年ごとにどのような内容を扱えばよいのかが記載されています。
また、現行学習指導要領から登場した「見方・考え方」は再整理される方向性です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
学びに向かう力、人間性等の再整理
「学びに向かう力、人間性等」は現行の学習指導要領から登場した言葉であり、理念としては大変重要だなと感じていますが、学校現場で落とし込んでいくのは非常に難しいと感じているところです。
そのような実態を踏まえ、再整理することが検討されています。具体的には「初発の思考や行動を起こす力・好奇心」等4つの要素により再整理するとしていますが、これがまた難解に感じます💦 詳しくは以下の記事をご覧ください。
なお、これはニュースになったのでご存知の方も多いと思いますが、「学びに向かう力、人間性等」を評価するための観点「主体的に学習に取り組む態度」は評定の対象から外れることになる方向性です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
柔軟な教育課程の導入
各学校の教育課程編成にあたっては、国が定める標準授業時数等を基礎としていますが、特例校に指定されれば、現在も柔軟な教育課程を編成することができます。
これを、特例校等の申請を不要とし、各学校の学力、不登校児童生徒数、特定分野に特異な才能のある児童生徒等の実態等を踏まえ、柔軟に教育課程を編成することができるようにする方向性です。これを「調整授業時数制度」とし、今後検討されていく予定です。
「柔軟な教育課程」のイメージは以下の記事をご覧ください。
不登校児童生徒等を包摂するための教育課程については以下の記事をご覧ください。
情報教育と探究的な学び
近年、情報関連技術が目覚ましく発展する中で、日本の学校における情報教育は国際的に不十分という状況であるとのことです。そのため、情報教育の充実を図ることが検討されています。
最も大きな変更としては、中学校の「技術・家庭科」の技術分野と家庭分野を分離し、「情報・技術科」(仮称)を創設する方向性です。ちなみに、家庭分野の細かい扱いについては今後検討される予定です。また、小学校から高校までの情報教育に系統性を持たせるとのことです。詳しくは以下の記事をご覧ください。
また、「総合的な学習(探究)の時間」を中心に行われている「探究的な学び」については、情報教育との親和性が高いということから、情報教育の充実と一体的に改善することが検討されています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
教科書の分量と高校入試
これまでの中教審の部会の中で「余白の創出を通じた教育の質の向上」ということも議論されてきました。その中で、教科書の分量や高校入試との関連性も議論されてきました。これは、僕が中学校教員であるから特に興味があることであり、大きな話題にはなっていませんが、紹介したいと思います。
まず、教科書の分量については以下の記事をご覧ください。
次に、高校入試改革については以下の記事をご覧ください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
次期学習指導要領策定に向け、様々な面で議論が進んでいますが、今回は中間点とも言える「論点整理」について書きました。
冒頭に書いたとおり、論点整理はかなりのボリュームであり、全ては紹介しきれていませんので、興味のある方は以下のページをご覧ください。